2022年6月1日
株式会社イースクエア代表取締役社長 本木 啓生
なぜトランジション経営なのか
私が仕事としてサステナビリティの分野を選んだのは1997年のことである。ちょうど京都議定書が発行された年でもあるのだが、「サステナビリティ」や「ステークホルダー」というコンセプトは専門家以外は知らず、環境とビジネスの関係はほぼ理解されていなかった時代であった。それから四半世紀が経ち、サステナビリティが多くの企業の経営課題のど真ん中に位置付けられるようになった。
国際社会は2030年をターゲットとしたSDGs(持続可能な開発目標)を設定したものの現段階では実態を伴った政策や取り組みには程遠く、人類社会の持続可能性を脅かす環境・社会課題は深刻度を増し続け、待ったなしの状況に陥っていることがその理由となる。国際的な企業開示のルールを決めるIFRS財団は、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)を設立し、IIRCとSASBそしてCDSBを統合、TCFD提言を採用し、さらにはGRIとも連携を図ろうとしている。サステナビリティの情報開示を巡り長い年月をかけて蓄積されてきた要素が集約され、企業開示のメインストリームに組み込まれることになる。昨年改訂されたコーポレートガバナンス・コードにも謳われているように、サステナビリティの専門部隊が対応してきた取り組みや情報開示が、取締役会マターへと昇華しようとしているのである。
どれくらいの変化を予測すべきか
ローマクラブが「成長の限界」を発表したのは、今からちょうど50年前の1972年である。研究チームは、人口増加、農業生産、再生不可能な天然資源の枯渇などの基本的な要因が、この地球上の成長を決定し、その相互作用によって最終的に制限されることになると厳しく警告した。しかし、誰にとっても対岸の火事であり、自分ごとには落とし込まれなかった。政府や企業は経済成長を最優先させ、資源を大量に消費する社会構造やビジネスモデルに歯止めをかけることはできなかったが、いよいよその延長線上に未来がないことが認識されつつある。
それではこれからどれくらいの変化を予測しておくべきなのであろうか。2019年のTFN海外遠征でロンドンのVolansを訪ねた際に、ジョン・エルキントン氏は「現在我々は、混乱と不確実性と恐れのゾーンに突入する入り口におり、その状態が12~15年続くと言われている。どうシフトするかは不確実というのが現状であり、今後10~15年はチャレンジングでエキサイティングな時代になるだろう。」とポジティブに語ってくれた。
ブレイクスルー・マインドセット

出典:ジョン・エルキントン氏によるプレゼンテーション資料
実際に、企業を取り巻く事業環境は急速に変わり始めている。前述したように資本市場において、サステナビリティ情報開示が実装されようとしている。サステナビリティ課題の中でも気候変動への対応は待ったなしとなり、どんなに遅くても2050年までにネットゼロを実現すべく各社は中長期目標の設定と具体的な方策の検討にしのぎを削ることになる。産業革命以前の平均気温からの上昇幅を1.5℃よりも低く抑えるためには、地球全体で2050年までにCO2の排出をネットゼロにする必要があるためである。TCFD提言では、企業にトランジション・プラン(移行計画)を開示することを求めている。つまり、低炭素社会への移行に伴うビジネス、戦略、財務計画への影響を検討することを求めているのである。化石燃料をベースに作られてきた近代社会を化石燃料を排除した社会に移行することは生やさしいことではない。
ビル・ゲイツの著書「地球の未来のため僕が決断したこと」によると、人間の活動によって排出されるGHGの量は、ものを作るとき(セメント、鋼鉄、プラスチック)に31%、電気を使うときに27%、植物や家畜などを育てるときに19%、飛行機やトラック、貨物船で移動するときに16%、暖房・冷房・冷蔵で7%を使用していると言うことだ。例えば、乗用車のEV化は急ピッチですすんでいるが、さらに難題となる大型トラック、貨物船も含むすべての移動手段を化石燃料を使用しない動力源に切り替えることに成功したとしても、全体から見ると16%の脱炭素化に過ぎず、残りの84%は別のアプローチが必要となる。そしてもちろんトランジションすべきものは気候変動対応だけではなく、水資源の枯渇や生態系の保全も必要だし、バリューチェーン上に潜む人権課題とも向き合う必要がある。
企業の強みと役割
社会・経済システムのトランジションにおける政府の役割は大きい。気候変動に関して、長期目標との一貫性を持った政策を常に打ち出しているのが英国政府である。同国は、2008年に気候変動法を制定し、目標達成の道筋を明確にするために、2050年まで5年ごとに向こう12年先までのGHG排出量の上限を定めたカーボン・バジェット(カーボン予算)を設定することが決められた。そして、気候変動法に基づき気候科学、経済、行動科学、ビジネスの専門家で構成された気候変動委員会(CCC : ClimateChange Committee)を設立し、気候変動対策の進捗をモニタリングし、政府に提言を出す役割を担わせた。昨年のCOP26において、金融機関と上場企業に対して、TCFDに則りネットゼロに向けたトランジションプランの開示を義務付けることを発表するだけでなく、グリーンウォッシュを防ぎ、トランジションプランを確実なものにするために新たなタスクフォース(UK Transition Plan Taskforce)を立ち上げた。英国政府は他国への支援も惜しみなく、2009年にイースクエアが日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)を設立した際にも、英国大使館から経済的な支援をして頂き、それが日本企業が気候変動に取り組むきっかけづくりともなった。
日本では現在、各省庁がこぞってサステナビリティ、SDGs、ESGに関する研究会を立ち上げ、提言をまとめている。そういった動き自体は好ましいのだが、長期的な視座に立った政策とはほど遠く一貫性はない。政策面において大いなる矛盾を孕んでいるのは他国も同様で、国際エネルギー機関(IEA)の推計では、化石燃料消費の政府補助金は、2018年には4,000億ドルに及んだと言うことだ。このような時代遅れの政府の補助金のことをブループラネット賞の受賞者であるノーマン・マイアーズ博士は、「邪悪な補助金(Perverse Subsidies)」と呼び、警告を発していたのは20年以上前のこととなる。
トランジションにおいて、企業は社会・環境問題の解決に必要不可欠な役割を果たすことができる。政府やNGO・NPOにはない能力が備わっているからである。それは、企業のみが政府や市民社会に資金を提供することができ、政府やNGO・NPOが実施できない方法で、多くの社会問題への解決策を生み出すことができるからである。また企業は、リスクを取るインセンティブを持っているし、健全な競争によりイノベーションや効率性が促されることになる。さらに、利益を確保することで、事業のスケールアップを図り、インパクトを増すことができる。
乗り切るために必要な視点
最後に、企業がトランジション経営を行うために大切だと考えている3つの視点について言及したい。
それは、長期的展望とシナリオ思考、そしてステークホルダー配慮である。
一つ目の長期的展望としては、経営上の様々な意思決定において時間軸を意識していく必要があるということである。例えば、CSV戦略を構築する際にも、少し長い目で事業を育てていくことが必要だ。特にCSVの3つ目のアプローチである産業クラスターあるいは別の言葉でビジネス・エコシステムへの取り組みは、事業そのものではなく自社を取り巻く事業環境へのテコ入れを行っていくことになるので、結果がでるまでに時間がかかる。
二つ目のシナリオ思考は、長期的展望とも関連するが、未来のあり方に強く影響を及ぼすドライビングフォースを意識して、確定要素と不確実性要素を整理しておくことである。不確実性要素の振れ幅により必ず複数の未来シナリオが想定されることになるので、長期戦略ではそのことを織り込んでおく必要がある。そして何より大切なのは、不確実性要素が確定要素に変化する瞬間を見逃さないことだ。つまり、不確実性要素として考えている間は頭の中のシミュレーションなのだが、確定要素になった瞬間に他社よりも早く実行に移す必要があるということである。例えば、サステナビリティ情報開示が企業開示の世界標準に組み込まれるということは、旧来は不確実性要素であったが、ISSBの発足により確定要素に切り替わったことになる。
最後のステークホルダー配慮は、株主資本主義からステークホルダー資本主義への見直しが始まっていると言うことだ。ステークホルダー軸では、顧客のみならず、従業員、取引先、国際機関など各ステークホルダーによる期待や要請を、経営判断の検討要素に加えていくことが求められる。様々なステークホルダーに配慮することが、中長期的な企業の価値創造につながり、最終的には株主にも還元できるという発想だ。
人類社会のサステナビリティに関する分水嶺に立つ我々は、これまでの社会構造やビジネスモデル、消費スタイルに別れを告げて、本格的なトランジションフェーズに飛び込む決断ができるかが問われている。
この記事は、(株)イースクエアが運営するサステナビリティ先進企業のネットワーク「フロンティア・ネットワーク」の季刊誌に掲載した記事です。
→フロンティア・ネットワークについては、 こちら をご覧ください。

→イースクエアのサステナビリティ経営支援については、 こちら をご覧ください。
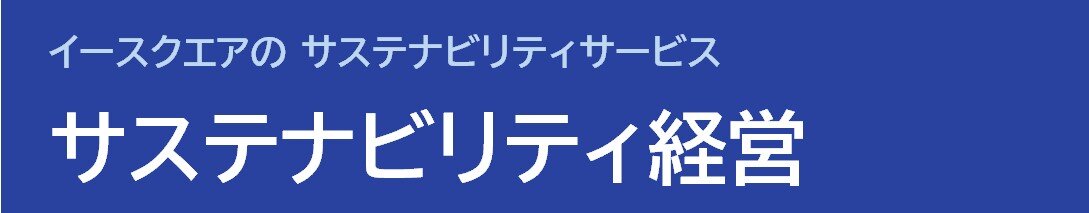
—–




